「てにをは」が正しく使えていないと、おかしな日本語になり、書き手の意図が読者に正しく伝わりません。この記事では、てにをはに関する基本的な知識から、正しい使い方まで、例文も交えながら分かりやすく解説します。
てにをはを正しく使って、意図を的確に伝えましょう。
てにをはとは

てにをはについての基礎知識として、以下の項目を解説します。
語句と語句をつなげる助詞の総称
てにをはとは、語句と語句をつなげる助詞の総称です。助詞には複数の種類があり、学説によって4~10種類に分類されています。主な助詞を以下にまとめました。
| 種類 | 役割 | 代表的な助詞 |
|---|---|---|
| 格助詞 | 体言に接続して、後ろに付く語句との関係性を示す | が、は、の、を、に、へ、と、から、より、で、や |
| 接続助詞 | 活用語に付いて、前後の語句をつなぐ | ば、が、ても、でも、けれど、のに、から、し、て、で |
| 副助詞 | 種々の語に付いて、意味を付け加える | だけ、ほど、くらい、まで、ばかり、など |
| 終助詞 | 文末に付いて、意味を付け加える | か、かしら、な、ぞ、ぜ、とも、の、わ、や |
助詞が単独で使われることはありません。つなげた語句の関係性を示したり、意味を付け加えたりする、文法上の役割があります。
てにをはの由来
てにをはとは、ヲコト点に由来する言葉です。ヲコト点とは、デジタル大辞泉には以下のとおり記載されています。
古く漢文訓読の際、漢字の読み方を示すために漢字の字面の四隅・上下・中央などに記入した符号。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
ヲコト点の四隅に書かれた「て」「に」「を」「は」が由来となっています。漢文の訓読において「てにをは」は、助詞や助動詞、接尾語、用言の語尾なども含む総称です。近年では主に助詞を指します。
「てにをはがおかしい」とはどういう意味?
「てにをはがおかしい」とは、助詞の使い方が不自然で、文章の意味や意図を理解しにくい状態を示します。語句と語句をつなぐ助詞が適切でないと、文章の意味が変わってしまったり、違和感を与えたりします。
例えば「その本を読んだ」と書きたい場面で「その本で読んだ」と書いてしまえば、意味が変わってしまい、相手に正しい情報が伝わりません。使用している助詞の誤りを正して、適切な表現を心がけましょう。
AIライティングツールを活用すれば、様々な言い回しのアイデアを簡単に収集できます。おかしな日本語を避けるためにも、積極的に文章に触れる機会を増やしましょう。
てにをはが示す意味と関係性を把握しよう

日常的によく使う副詞の示す意味を、例文とともに解説します。関係性を把握し、必要に応じて正しく使い分けましょう。
「が」と「は」
格助詞の「が」と「は」は主に主語に付きます。
「が」は主張や強調に効果的で、「は」は限定的な印象を与えます。
「が」と「で」
以下の例文の「が」と「で」は、気持ちや態度の意味を付け加える格助詞です。
上記例文の「が」には、その本を望む意思が感じられます。
一方の「で」は、本当はほかにもっと読みたい本があるように感じさせます。我慢や妥協、遠慮といったニュアンスで受け取る人もいるでしょう。場合によっては悪い印象を与えるため注意が必要です。
「が」と「を」
以下の例文の「が」と「を」は、意思や願望を示す格助詞です。
「が」の表現からは強い意思を感じられます。「を」は「が」よりもやや控えめでやわらかい印象を与えます。
「へ」と「に」と「まで」
以下の例文の「へ」と「に」と「まで」は、行き先を示す副助詞です。
「へ」は、これから向かうイメージがあるのに対し、「に」は今向かうといったイメージを抱かせます。「まで」を使うと、行き先の終点を表現できます。
「で」と「に」
以下の例文の「で」と「に」は、場所を示す格助詞です。
「で」は勉強する場所自体を示すのに対し、「に」は「勉強しに行く」という動作の目的となる場所や方向を示します。
てにをはの間違いを避ける方法

てにをはを間違えると、伝えたい情報や意図が正確に伝わりません。誤用を避けるために、以下の点を押さえましょう。
多くの文章を読んで慣れる
多くの文章を読んでいると、てにをはの使い方に慣れてきます。様々な文章に触れて、分かりやすい文章の流れを掴みましょう。
声に出して読む
文字情報だけでは気づきにくい誤りにも、声に出して読むと気づけます。音読して、てにをはに違和感がないか丁寧にチェックして修正しましょう。
ほかの人に読んでもらう
ほかの人に書いた文章を読んでもらうと、客観的に文章をチェックできます。てにをはの間違った使い方にも気づきやすくなり、効果的です。
Webライターとして文章力を向上させる方法をまとめた記事も参考にしてください。
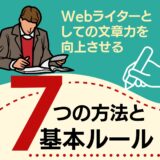
てにをはを正しく使って読みやすい文章に仕上げよう

文章で情報を的確に伝えるには、てにをはを正しく使うことが重要です。誤った使い方をすると、意味や印象が大きく変わってしまう場合もあります。
てにをはがおかしい文章にならないよう、間違いやすいケースを把握して、適切な助詞を選択しましょう。
間違いを防ぐためには、多くの文章に触れて使い方に慣れることが第一です。自分で声に出して読んだり、ほかの人に読んでもらったりして、違和感や誤解のない、分かりやすい文章を作成しましょう。
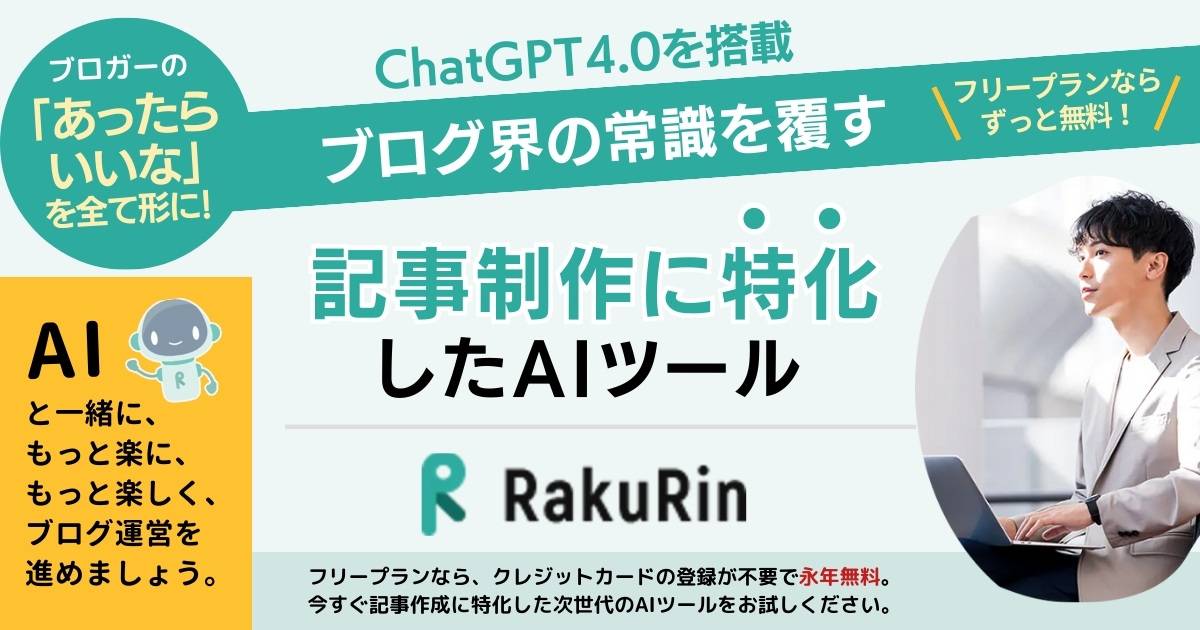
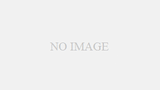
フリープランなら、クレジットカードの登録が不要で永年無料。
今すぐ記事作成に特化した次世代のAIツールをお試しください。
フリープランならずっと無料
無料で利用する