体言で文章を終えることを、体言止めと言います。修辞技法の一つです。体言とは、名詞や名詞句を意味します。
この記事では、体言止めの効果や使い方の例文を紹介します。活用時の注意点も解説しているので、効果的なライティングの参考にしてください。
体言止めの効果

ライティングの一手法である体言止めには、以下の効果があります。
- 強調する
- 余韻を残す
- 想像を促す
- 興味を引く
- リズムを付ける
体言止めにすると、体言がより強調され、読者に余韻をもたらす効果を期待できます。単調な文章に、リズムやテンポの変化を与えたい時にも効果的です。
体言止めの効果を示す例文

体言止めの効果を示す例文として、以下の3つの活用方法を説明します。
文末を変えてリズムを付ける
上の例文は、文末の「ます」が重複しており、単調で稚拙な感じがします。
体言止めにより、単調な文章が改善されました。
強調して余韻を残す
上の例文はそのままでも十分に意図が伝わりますが、体言止めにしてみましょう。
体言がより強調され、読者に強い印象を与えることができます。
興味を引いて想像を促す
上の例文を、体言止めで表現してみましょう。
「強い味方」と言い切ることで、興味を引き、読者の想像力をかきたてる効果が得られます。
体言止めを使う際の注意点

体言止めは効果的に活用できますが、使用については賛否が分かれるところです。
Webライターなどのクライアントワークでは、体言止めが禁止されているケースも多く見られます。禁止される主な理由は、体言止めの使用により、読み手の理解への負担を増やす可能性があるからです。
以下の注意点を押さえて、上手に取り入れましょう。
文章の流れを意識する
体言止めが連続すると、以下のように文章がぶつ切りになり、読みにくくなります。
上の例文は極端な例ですが、体言止めが多すぎると不自然でぎこちない文章になってしまいます。文章の流れを意識して、言葉のリズムを壊さないように適度に取り入れましょう。
伝わりにくくなる可能性がある
体言止めには余韻を残したり、イメージを広げたりする効果がある反面、内容が伝わりにくくなるデメリットがあります。
表現したいことが明確に伝わらなければ、読み手も迷ってしまいます。信頼性の高い記事を書くためにも、使うポイントを選び、曖昧な文章にならないように注意しましょう。
Webライターとしての文章力向上のために、以下の記事も役立ててください。
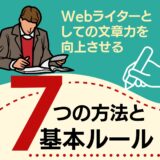
効果的に体言止めを活用しよう

体言止めは、体言を強調したり文章のリズムに変化を与えたりするのに効果的です。文末が重複してしまう時など、必要に応じて適度に取り入れ、単調なリズムの文章を改善しましょう。
クライアントワークでは、体言止めを禁止しているケースもあります。読み手への負荷を避けるためです。使い方によっては文章が伝わりにくくなったり、ぎこちない文章になったりするので、注意してください。
体言止めの使い方を覚えて、適度に、効果的に取り入れましょう。
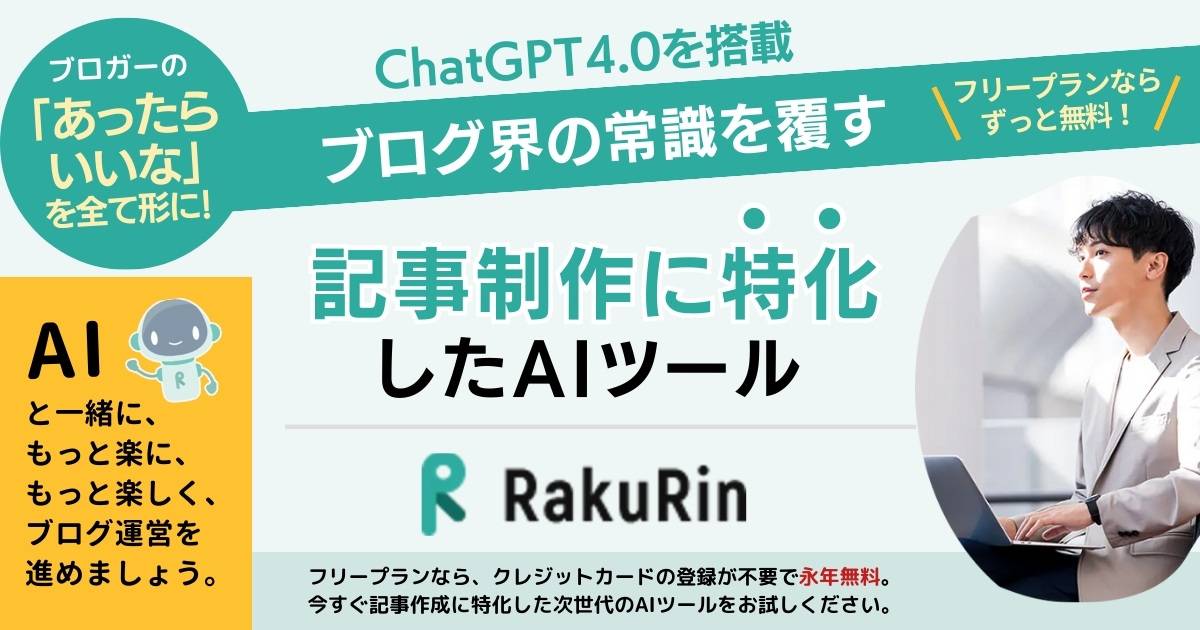
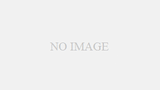
フリープランなら、クレジットカードの登録が不要で永年無料。
今すぐ記事作成に特化した次世代のAIツールをお試しください。
フリープランならずっと無料
無料で利用する